
コロナ禍以降初めてのバングラデシュでの映画配達が、2024年9月11日と12日の二日にわたり行われました。
・日にち:2024年9月11日・12日
・地域:バングラデシュ、チッタゴン丘陵地帯のバンドルボン
・場所:キニティウスクール(寄宿舎小学校)のキッチンダイニング
・上映回数:2回(二夜)
・上映作品:『FLY』『こまねこ はじめのいっぽ』『good night』『Jungle Beat』
・参加人数:40名
・参加した子どもたちの年齢:6 – 12歳
●上映場所は原田夏美さんが運営する寄宿舎小学校
バングラデシュでは、現地で子どもの教育支援を続ける原田夏美さん(ChotoBela woks)が、2018年から映画配達人として参画してくださっています。
バングラデシュの中でも、特に外国人の入域が厳しく制限され複雑な情勢が続く地域にあるのが、原田さんが運営するキニティウスクールです。
現地からお送りいただいたレポートと写真を挟みながら、今回の移動映画館のご報告をお届けいたします。

キニティウスクールでの移動映画館は、2019年に一度行われて以来で、現在の5年生にとって2度目の機会になりました。
「キニティウスクールは寄宿舎小学校で、教育にアクセスするために、5~12歳の子どもたちが親元を離れてここで暮らしています。キニティウとその周辺地域には未だ電気や水道も整いませんが、ネットはほんの少し届いており、キニティウスクールの敷地内でもネットが届く地点と届かない地点があったり、軍や政府によって遮断されたりすることもあります。」

「今回は初の夜上映で、映画体験はより臨場感があったと思います。」
キニティウスクールには歌やダンスをする「アクティビティクラス」があり、そのお手本を先生のスマホで見る時くらいが、普段、子どもたちが映像に触れられる時間だと言います。原田さんのもとへも「映像コンテンツを見られる機会がもっと欲しい」との声が届いてくるそうです。

「今回特に短編アニメの『FLY』から、子どもたちに気付き、感じてほしいことがたくさんあったので、一つ一つのシーンやメッセージを読み解くような見せ方もしたいと思うし、『good night*』のようなタイプの映像作りをやはり実践で教えたいとも思いました。」
*『good night』は手書きのイラストタッチで制作された2Dアニメーション作品です。
●子どもたちからの感想
Manhoi Khumi, Class 5(マンホイ クミ、5年生)

こんなに大きい映像を見たのは、生まれて初めてでした。アニメから学ぶこともできました。(『Fly』のクライマックスのシーンを見て)私は自分の死んだお母さんを思い出して泣きました。
映画を運んでくれたお姉さんたちへ、ありがとうございます。
Paiyen Mro, Class 5(パイエン ムロ、5年生)

お姉さんたちが素敵な作品を見せてくれて、とても嬉しかったです。みんなで一緒に楽しみました。いつもは見ることができず残念です。学校にスクリーンやテレビがあったら、もっといっぱい見られるのにな。
Koni Khumi, Class 2(コニ クミ、2年生)

『Good night』のように、僕もアニメを見た後、夢を見ました。アニメの子どもたちは僕みたいにいたずらっ子ですが、彼らは歯磨きをしていました。僕はあんまりしないので、今日から毎日歯磨きしようと思いました。

●移動映画館の新たなコラボレーション
実は今回、キニティウスクールでの移動映画館を実現しくれたのは、原田さんと親交の深いRuwang Collective Artsのメンバーでした。チッタゴン丘陵地帯の少数民族出身の大学生を中心に発足した活動です。
彼らもまたWTPに通じる理念を持ち、少数民族の暮らす地域に映画を届ける「Cine CHT (Chittagong Hill Tracts)」というプロジェクトを立ち上げ活動を行っています。
今回実際に映画配達を担ってくれたメンバーのお二人からも感想をいただきましたのでご紹介させていただきます。
Snighdha, Student at Pathshala South Asian Media Institute(スニグダ、パッシャラ(写真科) の大学生)
キニティウスクールでの上映会は、寄宿舎の部屋や食堂を即席の映画館に変身させて行いました。
子ども達にとって大きなスクリーンは幻想的で、映画が始まると喜びの叫び声をあげ、見ている間は完全に押し黙って没入していました。子ども達はスクリーンの中に生きるアニメーションのキャラクターに興奮と好奇心でいっぱいで、笑い声をあげながら見ていました。
電気のないところで実現することは大きな挑戦でしたが、私たちも楽しみながら協力し合うことができ、笑いにあふれた時間でした。
上映したのはシンプルな楽しいアニメ作品と、2本の感動的な短編作品です。
上映後、私たちが感想を聞くと子ども達は恥ずかしがっていました。
Paddmini, Student at Pathshala South Asian Media Institute(パドミニ、パッシャラ(写真科) の大学生)
キニティウでの映画上映会は素晴らしい経験になりました。
映画が始まった途端、子ども達の興奮が目に見えてわかり、とても楽しんでいることが伝わってきました。
私自身にとって今回の機会の中で得たとても大切な気づきは、自然と見えてくる学びのプロセスでした。
映画は単なる娯楽ではない−子ども達に好奇心を起こさせ、新しい視点から考える力を呼び起こすものです。
彼らは楽しみながら学んでいて、それこそがこの映画上映会の本当に素晴らしい部分だと思いました。
一つ気づいた点としては、子ども達は初めての人と出会った時にとても恥ずかしがり屋でした。
この上映会はそういう点でも、なかなか他にない形で彼らとの接点を結んでくれました。
一緒に映画を見るということだけでなく、緊張をほぐしてくれ、言葉を交わすきっかけをくれ、お互いに心地よい輪を作ってくれました。
この上映会が私たちと子ども達の間の架け橋となってくれ、会話が始まる手助けしてくれました。
それは他の形ではなかなか難しいことだったと思います。
このような上映会というものは、楽しくリラックスできる環境の中で繋がり合い思いをシェアできる特別な方法なのだと感じました。

今後も原田さんそしてRuwang Collective Artsの皆さんのお力を借りながら、バングラデシュでの移動映画館を行なってまいります。
次回バングラデシュからは、年末年始に開催された第6回チッタゴン丘陵映画祭のご報告をお届けする予定です。
今後もバングラデシュでもより多くの子どもたちに映画を届けられるよう、みなさまからのご支援をお待ちしております。


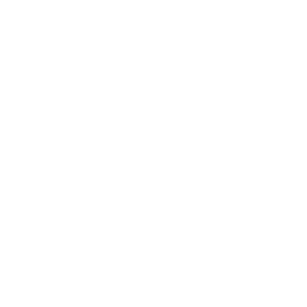
コメント